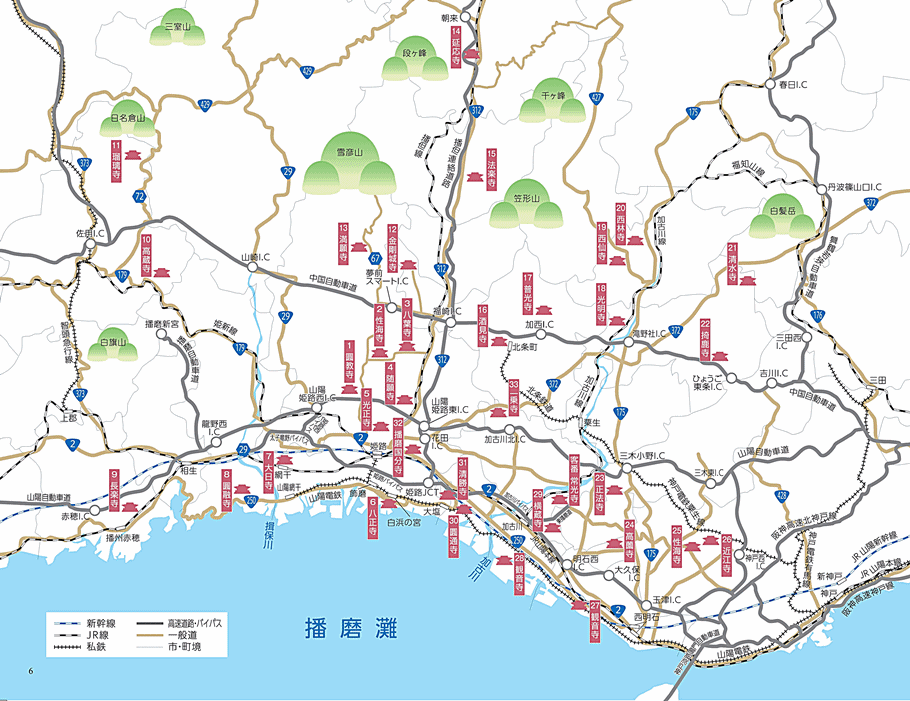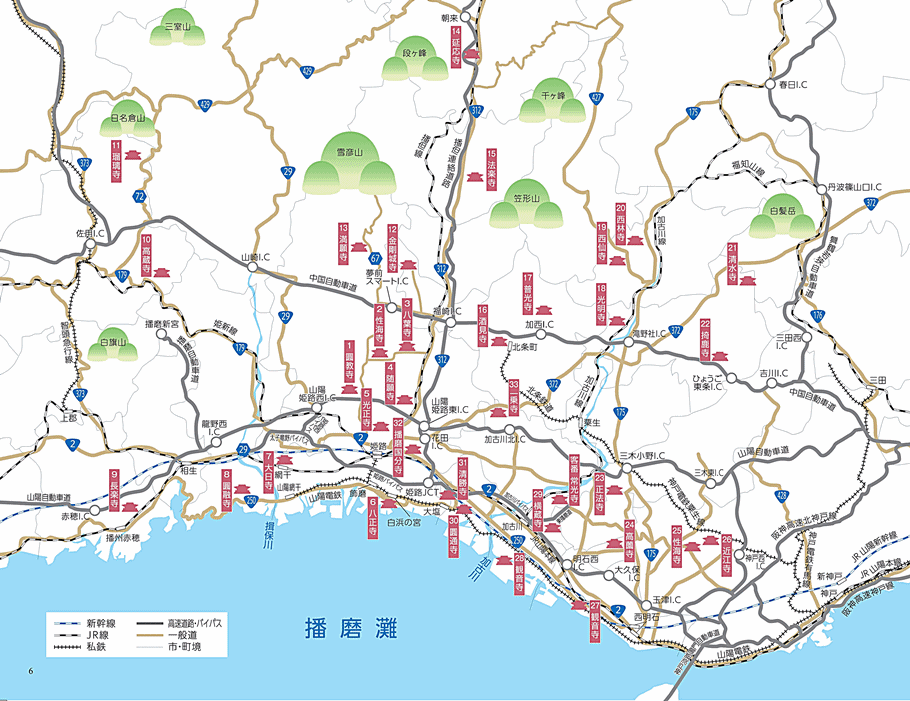|
南室和尚願文
恭しく惟るに観音薩埵を順礼するの由来は、那智山順礼記に曰く、往昔徳道上人入滅の時間家の老子に見え種々の功徳を讃嘆す、時に闇老徳道に告げて曰く娑婆世界に於て生身の観音三十三所の座、四重五逆の人阿鼻地獄に堕す可きあるも、一度彼の宝前に参詣するの輩は無始よりの生死の罪を滅し九品の浄土に生ず可きなり、此れは是れ諸善最上の功徳根本の法なり、今汝に付属す急ぎ本土に走り一切の衆生を教示すべし、然る後七日あり蘇生し来って普く世に伝ふ、乃ち本朝の西国順礼是れなり、知隣も亦其跡を追ふて謹んで上聞に達す、補陀を当国十六郡の内に尋ね、詠歌を西国三十三所の式に準ず、遮幾くは諸人一心に観世音菩薩を念して順礼恭敬し当に此の歌を唱え強いて能く順行唱歌礼拝供養せば、過現当来諸天擁護して悪を去り邪を駆し宅を鎮め国を安んずべし、故に経に云く、一切の功徳を具して慈眼をもって衆生を視福聚の海無量なり是の故に応に順礼すべし、誠なるかな此の言や、夫れ唱歌は古今の序に云ふ、天地を動かし鬼神を感ぜしめ人倫を化し夫婦を和すは和歌にしくはなし云々、其の読むや其の唄ふや其の悟りに到れば則ち一なり、願くば此順礼の功を以て四恩に報い三有を済ひ、一切諸を衆生を皆な上品の蓮台に登らしめんことを
寛文五乙巳年(一六六五年) 隣南室叟誌焉
|